こんにちは。
通級担当として、10年以上・100人以上の指導歴がある「ねこもみじ」です。
今回のテーマはこれです。
通級での教材選びをどうするか?
あなたの学校、というか手元には通級で使える教材はありますか?
まぁ、普通に考えたらありますよね。
では聞きますが、あなたはその教材を効果的に活用できていますか?
どうでしょうか?
本記事を読むことで、
教材を「選ぶ」と「活用する」の違いと、教材を選ぶ時の2つのポイント
が分かります。
「SNSで『いいよ!』と紹介されていたから…」みたいな理由で安易に教材を選んでいませんか?今回は、教材を「活用する」とはどういうことかをお伝えしていきます。
通級での教材「活用」が難しい3つの理由
まず、前提から。
通級において、教材を「知っている」ことと「活用する」ことは全く違う。
どういうことか?
「知っている」とはこんな状態です。
- SNSで流れてきた情報の中に役立ちそうなプリントがあった
- 研修会で「この本、いいですよ〜」と紹介があった
- Amazonで「通級 教材」と検索したら、上位表示された本があった
こういうのが「知っている」ですね。
はい、あなたもどれかには当てはまりましたね(笑)
私も昔は当てはまってましたよ。
まぁ教材を知らないことには通級での指導に使えないので、確かに「知っている」ことも大切です。それはその通りです。
では、「活用する」とは?
- 教材の中から、目の前のその子の発達段階や興味に合わせたプリントを使う
- 一教材の中から、目の前のその子の強みや弱みを踏まえて難易度を調整する
- 指導中に、目の前のその子の反応や取組スピードを見てプリントの順番を入れ替えたり枚数を調整したりする
これが、通級において教材を「活用する」です。
違い、分かりますか?
言い換えると…
- 知っている:教員目線。「使ってみたいから選んだ」
- 活用する:子ども目線。「その子がクラスで力を発揮するために選んだ」
この差なんです。
とは言っても、分かっちゃいるけど教材を「活用する」って難しいんですよ。
私も悩んでいるし、たぶん全国の通級担当はみんな同じだと思う。
じゃあ、何で難しいのか?
理由は3つあります。
- ①子ども側の変数が多すぎる
- ②環境側の変数もある
- ③効果が分かりにくい
教材活用の難しさ①:子ども側の変数が多い
- 何年生?
- どんな特性がある?
- 診断はある?
- 心理検査は受けている?
- 心理検査の結果から分かる発達/知的水準は?
- 興味や関心があることは?
- 男子/女子?
- どんな性格? など
・・・・・・・・はい、もういいですね(笑) 他にもあるだろうしね。
これらの内容=子ども側の変数を踏まえて指導しなくてはならない。
これが、教材活用の1つ目の難しさです。
教材活用の難しさ②:環境側の変数もある
子ども側の変数だけでなく、環境側の変数もあります。どういうことか?
- クラスでの困り感はいつどこで?(授業?休み時間?給食や掃除?)
- トラブル相手は誰?
- 担任はどんな先生?
- 保護者のニーズは? など
これらは子ども自身の内容ではなく、子どもと周囲との関係性=環境の内容です。
つまり、環境側の変数です。
子ども側の変数に加えて、環境側の変数も踏まえて指導しなくてはならない。
これが、教材活用の2つ目の難しさです。
教材活用の難しさ③:効果が分かりにくい
ある程度、子ども側の変数も環境側の変数も考えて教材を選んでみた。
子どもの反応なども見ながら、3〜4回指導してみた。
でも…変化は…よく分からない。
クラスでの変化なんて、もっと分かりにくい。
指導した効果が分かりにくい。
これが、教材活用の3つ目の難しさです。
もしかしたら、3つの難しさの中でこれが一番ハードルかもしれないですね。
通級での教材選びの2つのポイント
「難しいのは分かった。というか、もう分かってた。じゃあ、どうすればいいの?」
ここが知りたいところですよね。
もちろん、全ての子にハマる「正解」なんてものはありません。
あれば私が知りたい(笑)
もしあるなら、お金を出してでもそれを買ってすぐにこのブログで紹介する(笑)
でも、そんな「正解」はないんです。
残念ながら。
だから日々、あなたはもがき・苦しみ・試行錯誤しながら頑張ってるわけです。
ただ、正解はないんだけど教材選びの2つのポイントはお伝えできます。
- ①WISC-Ⅴ知能検査に対応させる
- ②低・中・高にざっくり分ける
教材選びのポイント①:WISC-Ⅴ知能検査に対応させる
もし手元にその子のプロフィール(※検査結果だと思ってください)があれば、ラッキー!!
え? 難しい用語とか数字とかありすぎて、あまり見てない?
もったいない(笑)!
用語の理解や数値の解説まではできなくても、数字などをざっと見てぜひ教示選びのヒントにしていきましょう。
- VCI(言語理解)が低い:言葉や語彙を増やすプリント、概念形成(例:赤い果物は?)を高めるプリントなど
- VSI(視空間)が低い:線や形を正確に描き写すプリント(例:点つなぎ)、タングラムや数〜数十ピースのパズルなど
- FRI(流動性推理)が低い:簡単な数独・ナンプレのようなプリントなど
- WMI(ワーキングメモリー)が低い:聞き続ける・記憶するプリント、なぞなぞなど
- PSI(処理速度)が低い:数字や形を素早く書き写すプリント、左右の形の違いを素早く見極めるプリントなど
まっ、こんな風に書いても伝わりにくいですよね…(笑)
詳細は、また別の記事で解説しますね。
ここでは、WISC‐Ⅴの結果と対応させたら教材選びがしやすくなる。
これだけを覚えておいてください!
教材選びのポイント②:低・中・高学年でざっくり分ける
いろんな教材が売られていて、その中でも「◯年生」とか書いてあるのありますよね?
あれ、地味に助かりますよ。
なにせ、教材選びで難しい部分を著者や出版社が担ってくれているわけですから(笑)
もちろん、鵜呑みNG。
「目の前のその子の実態に合わせて教材を選ぶ」。
これが大前提です。
なんだけど、それでもどうやって教材を選べばいいか分からん…という場合は、低・中・高学年とか◯年生でざっくり分けると選びやすい。
これも知っておいたらいいポイントだと思います。
まとめ
教材は「知っている」だけじゃ意味がない。
「活用」してこそ力になる。
ただし活用は難しい。
子どもの変数、環境の変数、そして効果の見えにくさがあるから。
でも――
WISC-Ⅴをヒントにすること、低中高で分けて考えること。
この2つを押さえれば、教材選びはぐっとラクになります。
正解はない。
だからこそ、悩みながら選ぶしかない。
でもそれでいいんです。
あなたも、私も、同じように悩みながら進んでますから。
悩まないことの方がよっぽど怖いです。
一緒に頑張っていきましょう。
👉 関連記事:
- 通級担当がぶつかる壁①【役割・振る舞い・心得の悩みと乗り越え方】
- 通級担当がぶつかる壁②【子どもへの指導の難しさと乗り越え方】
- 通級担当がぶつかる壁④【保護者対応の難しさと信頼関係の築き方】
- 通級担当がぶつかる壁⑤【メンタルの保ち方と続けるための工夫】
👉 通級ラボのトップページはこちら
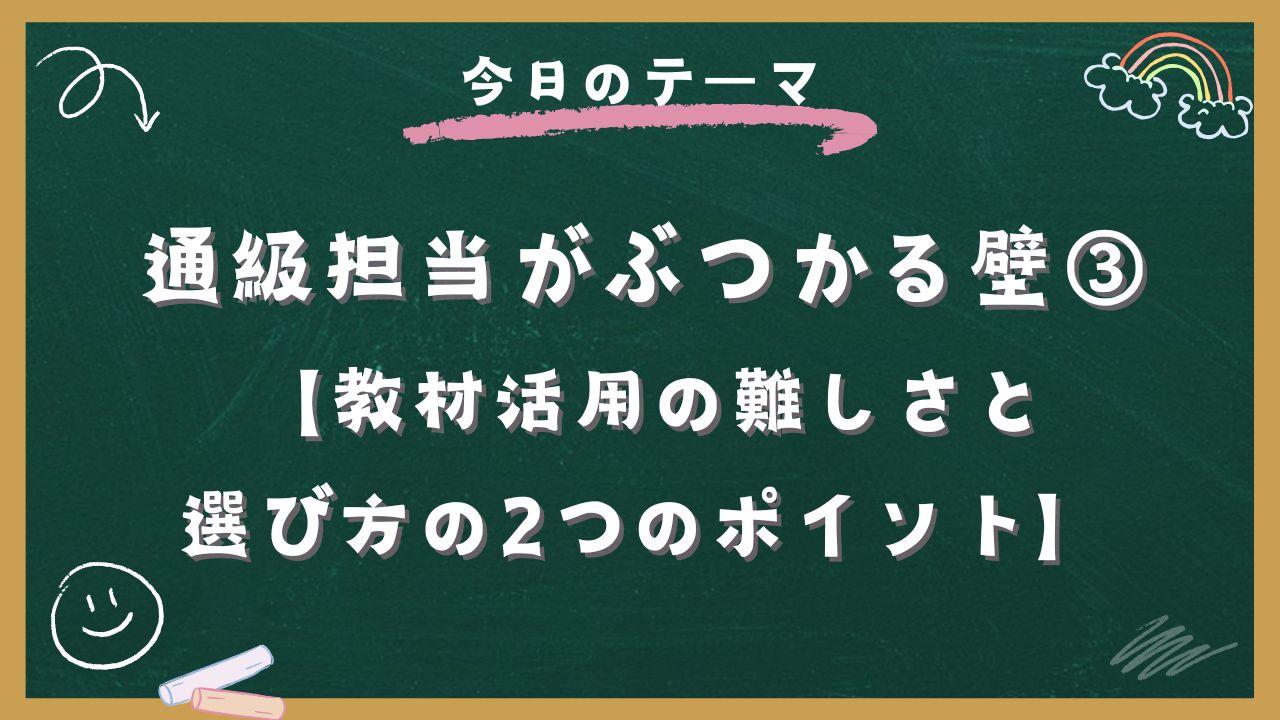
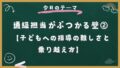
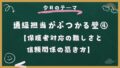
コメント