こんにちは。
通級担当として、10年以上・100人以上の指導歴がある「ねこもみじ」です。
今回のテーマはこれです。
保護者との信頼関係をどう築くか?
本記事を読むことで、
保護者対応はなぜ難しいのか。どうやって保護者と信頼関係を築けばいいのか。
が分かります。
教員をやっていたら永遠のテーマの一つですよね〜、「保護者」(笑)
担任をやっていた時も保護者との関係性は重視していたつもりですが、通級担当になってからは更に重視していました。
それはどうしてなのかや、そもそも保護者と信頼関係を築くのは難しいといったことをお話します。
保護者対応が難しい理由
保護者対応。
ほごしゃたいおう。
嫌な響きですね…どう考えても不吉な要素が含まれていそうで…(笑)
でも、なんで保護者対応ってネガティブなんでしょうか?
考えられそうな内容を以下に挙げてみます。
- アポなく急に連絡(※電話や連絡帳、訪問など)がある
- 時間をとられる(※1回に1時間とかはふつう)
- 複数回対応しないといけないこともある
- 場合によっては家庭訪問をする必要がある。それも複数の家庭に
- 自分が責められているような気になる
- 自分のメンタルが弱っていく。その日だけでなく、翌日以降も引きずる など
教員の一番の仕事・業務は何でしょうか?
いろいろな意見はあるにせよ、「子どもへの指導」であることは間違いないでしょう。
しかし、上に挙げた内容は直接子どもに関わることではありません。
子どもの保護者に対することです。
一般的な仕事において、目の前のお客さんにサービスを提供することに加えて、その場にはいないお客さんのご両親にまで配慮してサービスを提供する。
または、ご両親は後日対応する。
こんな仕事はあるのでしょうか?
あるのかもしれないけれど、私はすぐに思いつきません。
つまり、教員の業務内容は結構特殊なのではないかと思うんです。
目の前の子ども達の指導を毎時間行うだけでなく、保護者への説明や対応も頭に入れながら過ごさないといけない。
これが教員が嫌がる「保護者対応」の難しさ中身と理由です。
通級担当の場合は、一人ひとりとの関係性が強く深くなる分、保護者との関係性も強く深くなります。
通級担当にとって、保護者との関係性はより大切で難しいと言えるでしょう。
通級における保護者と信頼関係を築くメリット
保護者と信頼関係を築く時間も労力ももったいない。
極力関わる必要はない。
このような意見もあるでしょう。
そして、教員の業務内容を考えるとそれも一理あると思います。
ただ、通級担当が保護者と信頼関係を築くことはメリットしかない、と考えています。
その理由は何か?
そして、通級担当として保護者と信頼関係を築くことはどんなメリットがあるのか?
以下に挙げてみます。
- 目の前のその子に明るく接せられる
- 楽しく気持ちよく仕事できる
- 通級で学ぶことに対して、その子がポジティブになる
- 「この指導をしても、この保護者は理解してくれる」と安心感をもてる
- 保護者が家庭でもその子に支援する機会が増える
- 通級担当と担任や学校に加えて、保護者もチームの一員になる など
えーっと、いいことしかないですね(笑)
明るく前向きに指導ができるし、安心感があることで「この指導をやってみよう。だめなら修正すればいいや」とチャレンジすることもできる。
通級担当は、
保護者と信頼関係を築くことで、(基本的には)メリットしかない
これはとてもポジティブな事実です。
通級における保護者と信頼関係の築く3つの方法
保護者と信頼関係を築くなんて…とても難しそう。
そもそもどうやって?
以下に紹介する方法があなたにハマるかどうかは分かりません。
でも、何かしらの「きっかけ」や「ヒント」にはなると思います。
ぜひ、試して・修正して・何回かやってみて・自分のやり方に落とし込んでいってくださいね。
①その子がクラスで変化し始めた・していることを見つける
「その子がクラスで変わってきた」という事実。
これが一番強いと思います。
担任が話すエピソードでもいいし、その子のプリントやテストでもいいし、あなたが観察に行った時に見た内容でもいい。
少しでもその子がクラスで「変わってきている」という事実を見つける。
事実は嘘をつきません。
事実は強い説得力があります。
まずはこれを必死で見つける。
多少強引な関連付けでもいいと思います。
事実を見つけなければ、保護者には何も伝わりません。
②共有する時は、連絡ノートや連絡ファイルを使う
クラスでの事実を見つけても、なかなか共有する機会がないかもしれません。
担任だったらまだしも、通級担当の私がいきなり保護者に電話をかけるのも…という気持ちもよく分かります。
そして忘れがちなんですが、電話というツールは相手の時間を強制的に奪います。
電話をかける側は楽なんですが。
しかも電話では何を話されたのか文字として残らないため、保護者からしたらデメリットの方が大きい。
なので、その子の変化を保護者と共有する時は
文字として残り保護者が好きなタイミングで読んだり何度も読み返したりできる「連絡ノート」や「連絡ファイル」を使う
ことが大事です。
既に使っておられる先生も多いでしょうね。
古典的なツールかもしれませんが、保護者からしたら電話よりもメリットが多いし、デジタルに疎い保護者もいますから今でもすごく有用です。
③一定期間ごとに関係者で面談をする
②で紹介した方法はどちらかと言えば「短期間の頻繁な共有の方法」です。
週1回の頻度で指導していたら、週1回の頻度で連絡ノートを書くでしょうから。
でもよく考えてください。
そんなに毎週毎週その子はクラスで変化していますか?
していませんよね(笑)
短期間でそんなに変化するなら、通級での指導に悩む必要もないし。
でもそうじゃないから悩むんですよね。
そこでオススメするのは、
一定期間ごとに、関係者で面談する
方法です。
一定期間とは、例えば学期末ごとですね。
年に3回か〜多いな〜と思ったあなたは、半年に1回でもいいと思います。
9月と3月とかね。
何が言いたいかというと、「中・長期的に、そして定期的に共有する」ことが大事なんですよ、ということです。
毎週毎週その子のクラスでの変化を見つけることはさすがに難しいです。
でも、3ヶ月間〜半年間というスパンだと見えるその子の変化も違ってきますね?そしてその変化を「面談」で行うことに意味があります。
なぜなら面談は、
- 関係者が物理的にも時間的にも、
- 一同に介して、
- 会話をしながら、
- その子の変化(や課題)を共有する
という場だからです。
保護者にすれば電話と違って面談は「意識して時間を作って行く場」です。
だから、マインドセットから違ってくるわけです。
その面談で、その子のポジティブなクラスの変化を共有できたら?
保護者と信頼関係が築けること間違いなしです。
まとめ
保護者対応はしんどい。
これはもう間違いないです。
でも考えてみてください。
「対応」だからしんどいんです。
後手に回っているから。
そうじゃなくて、自分から信頼を掴みにいく。
ツールや面談を活用して。
そうすれば保護者は敵じゃなく、味方・チームになってくれる。
保護者がチームになれば、通級担当としての仕事はぐっと楽になるし、何より楽しくなる。
楽しみながら仕事できる――こんなに幸せなこと、ありますか?
正解はありません。でも、
- 事実を見つけて共有する
- 文字に残す(※短期的に共有する)
- 定期的に面談する(※中・長期的に共有する)
この3つを意識するだけで関係性は変わります。
大丈夫。
あなたの誠実な姿勢は保護者に伝わりますよ。
誠実で頑張っている人間の頑張りは、必ず伝わるものだから。
一緒に頑張っていきましょう。
👉 関連記事:
- 通級担当がぶつかる壁①【役割・振る舞い・心得の悩みと乗り越え方】
- 通級担当がぶつかる壁②【子どもへの指導の難しさと乗り越え方】
- 通級担当がぶつかる壁③【教材活用とは?そして教材選びの2つのポイント】
- 通級担当がぶつかる壁⑤【メンタルの保ち方と続けるための工夫】
👉 通級ラボのトップページはこちら
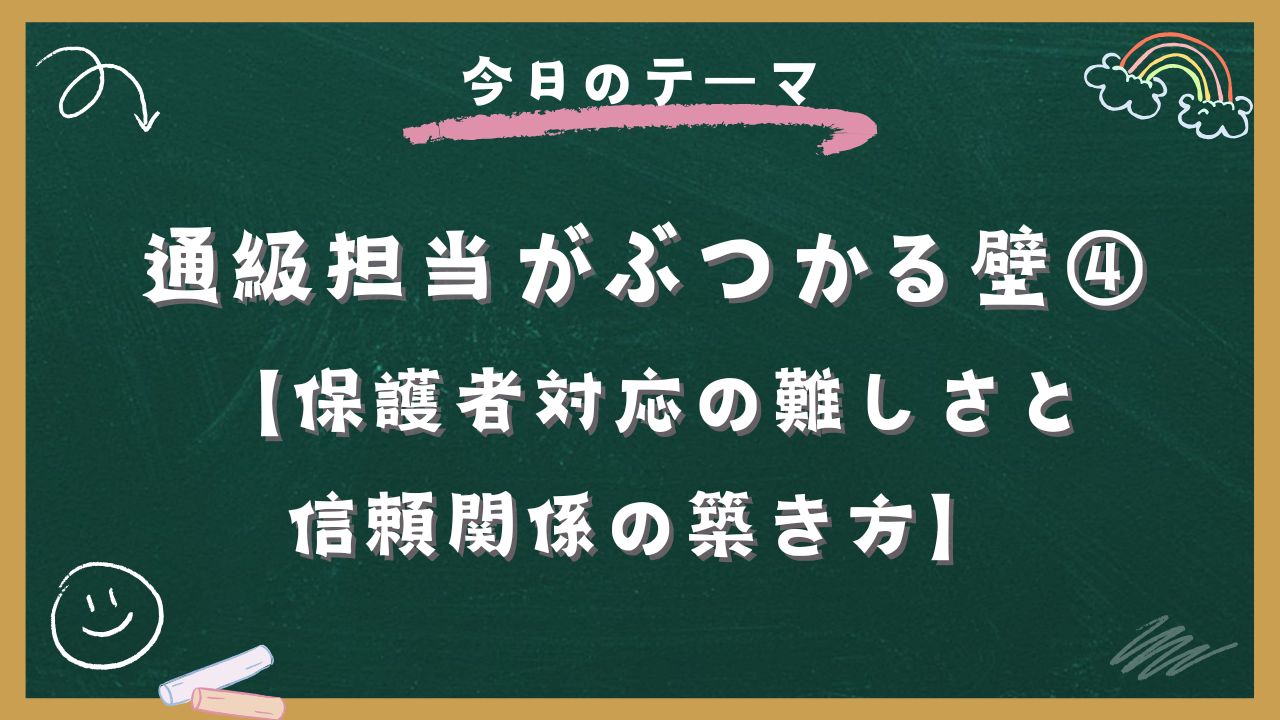


コメント