こんにちは。
通級担当として、10年以上・100人以上の指導歴がある「ねこもみじ」です。
今回のテーマはこれです。
なぜ私が通級担当になったのか?
「・・・興味ねーよ」とか言わないでください(笑)
私が経験してきたことは、きっとあなたの経験と共通部分があると思います。
本記事を読むことで、
通級担当として大切な視点は何か?
が分かります。
フェーズ1「学級担任」:集団の中で子どもを伸ばす視点
担任として大切な視点はこれです。
学級という集団の中で、子ども達をどう伸ばすか。
普通に考えれば、学級には30人程度の子ども達がいます。
どれほど小規模の小学校でも、クラスに2人以上はいます。
だから、学級=集団なわけです。
この「集団」の力はすごい。集団のダイナミクスとも言えばいいでしょうか。
- 1人の発言がきっかけとなり、授業の深みや内容の理解が深まった
- 1人ではできない・やろとしない子が、みんなの励ましにより取り組めた
- 4月はバラバラな集団だったのに、3月にはみんなで助け合える集団になった
ほんの一例を挙げましたが、こういった経験は担任をされたことのある先生方であればきっとあるはず。
集団ならでは、ですよね。私は「集団のダイナミクス」こそが、学級の良さだと考えています。
私の教師生活のスタートは担任からでした。あなたもそうですか?
毎日、子どもたちの笑顔や泣き顔、成長の瞬間を間近で見ながら授業や生活指導に全力を注ぐ日々。
特に、3年目までは本当にがむしゃらでした。
良いと聞いた教材や指導法はすぐに取り入れ、実践しまくっていました。
それでも、上手くいかないことばかり…。
ただただ毎日をやり過ごすことで精一杯。
今思い返せば、とても苦しい日々でした。すごくしんどかった。
でも、良いこともありました。それは、
集団の中で子ども達は伸びる。集団の力はすごい。
に気付けたことです。
そしてこの視点こそが、学級担任の視点ではないかと考えるようになりました。
フェーズ2「特別支援教育コーディネーター」:学校全体を見渡し、個別支援を考える視点
初めての異動を経験して3年目、私は特別支援教育コーディネーターの校務分掌を任されました。
それまでは主に体育的行事とか特別活動とかを担当していましたから、まぁまぁな出来事だったと思います(笑)
ただ、今になって振り返ると両者には共通点もありました。
それは、
「学級や学年を越えて、学校を見渡し動かす」
ということです。
体育的行事や特別活動も特別支援教育コーディネーターも、子ども達へのアプローチは違っても「学校を動かす」という点では同じです。
体育的行事だったら運動会とか、特別活動だったら児童会活動とかですね。
特別支援教育コーディネーターであれば、学校全体を見渡して担任や保護者と連携しながら子どもの支援方針を決定・調整するとかですね。
特別支援教育コーディネーターとして私は、改めて「学級や学年を越えて、学校を見渡し動かす」大切さと重要性を学べました。
さらにもう1つ学べたことがあります。それは、
一人ひとりに合わせた支援を考える
ことです。
つまり私は、特別支援教育コーディネーターとして「学級や学年を越えて学校を見渡し」ながら、「一人ひとりに合わせた支援を考える」ことをやっていたわけですね。
全体を見ながら、個を見る。
一見真逆のことをやっているように思えますし、実際そういう部分はあるのかもしれません。
相反するような「全体を見ながら、個を見る」経験。
この経験が、のちに通級担当につながっていきました。
フェーズ3「通級との出会い」:個別指導の重要性と通級の可能性
実は担任時の私は、通級に対してこんな思いを持っていました。
通級って何をしてるのか分からない…1人しか相手にしてないし、めっちゃ楽なんじゃ…。
あなたはこんな風に思ったことはありませんか(笑)?
えっと、きっと1回はあります。…よね(笑)?
そんな私の考えが変わっていったきっかけは、担任していた子が通級を利用していたからです。
通級で具体的に何をしているのかはよく分からなかったんですが、その子は毎回楽しそうに通級に行って、楽しそうに帰ってきてたんです。
- ボードゲームばっかりしてんのかな?だから楽しいのかな?
- さすがに45分間ずっと遊んでるわけじゃないよな。何してんのやろ?
- ちょっとずつではあるけど、この子変化してるよな。
自分の中で、通級に対していろいろな思いや疑問、興味が出てきました
ちょうどその頃、私は学級での全体指導に限界を感じ始めていました。
どう頑張っても、学級全員の力を一律に高めることは難しい…。
子ども達の限界という意味も、私の指導力の限界という意味も、両方を含んでいます。
だからこそ、「個」に応じた指導で力を伸ばす通級に惹かれ始めていたのだと思います。
そんな折、管理職から「通級担当をやってみないか?」と声がかかりました。
私の返事は、「はい、やってみたいです」。
…とかっこよく書きましたが、ここから大変な日々が始まりました(笑)
まとめ
学級担任としては「学級という集団の中で、子ども達をどう伸ばすか」という視点。
特別支援教育コーディネーターとしては「学級や学年を越えて、学校を見渡し動かす」という視点。
そして、「全体を見ながら、個を見る」という視点。
これらの視点は、通級担当としてすべて大切です。
これらの視点を持ち合わせる・意識できることで、目の前のその子の力を最大限引き出して伸ばすことができるんです。
これらの視点を既に持っておられるあなたも、まだ持っていない・意識できていないあなたも。
大丈夫。
日々、意識することで身につけることはできます。
一つずつ取り組んでいきましょう。
一緒に頑張っていきましょう。
👉運営者の詳しいプロフィールはこちら
👉 通級ラボのトップページはこちら
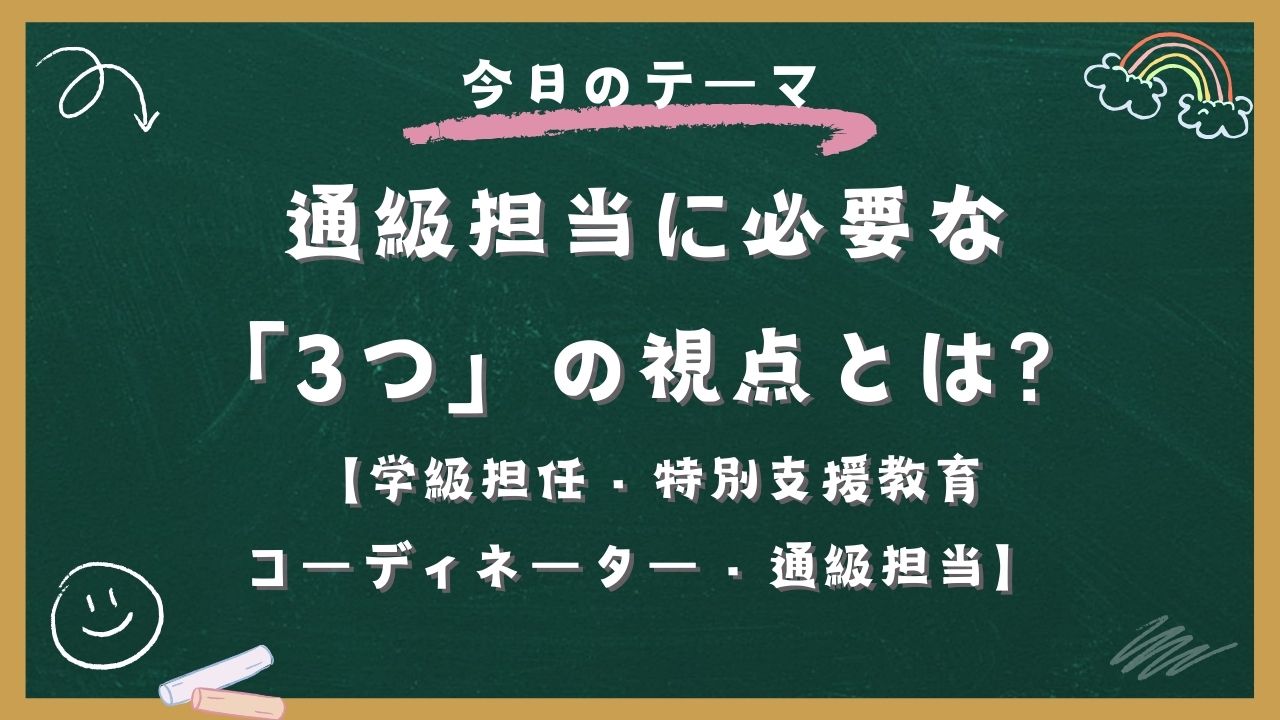
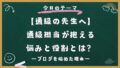
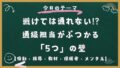
コメント