こんにちは。
通級担当として、10年以上・100人以上の指導歴がある「ねこもみじ」です。
今回のテーマはこれです。
通級担当がぶつかる壁①を乗り越えるにはどうしたらいいか? ーその1ー
(※「ぶつかる壁①って何?」と思われた方は、こちらの記事を読んでくださいね)
本記事を読むことで、
通級担当としてどう振る舞えばいいのか
が分かります。
通級担当は、学校組織の中でも特殊な立場。
だからこそ、学級担任とは違う特殊な振る舞いやマインドセットが必要です。
その1つ目の具体を、今回は見ていきましょう。
(※2つ目の具体は、こちらです。合わせて読んでください)
通級担当の振る舞いスキル【職員室・行動観察・指導】
私はあえて「振る舞い」という用語を使います。
それが一番しっくりくるからです。
ただ、「あざとい」等と感じる人もいるでしょう。そんな方は通級担当としての考えや思いを「行動で見えるようにする」と言い換えてください。
考えや思いは行動という目に見える形になることで相手に伝わります。
その意味で私は「振る舞う」という用語を使います。ただ、「行動で見えるようにする」でもかまいません。
では、実際にどんな風に振る舞えばいいのか? 実際の職場を想定して、3場面に分けてお伝えしますね。
場面①:職員室
一番大事です。職員室。だって担任だけでなく、いろいろな先生がいるから。
通級担当としてのあなたの言動を、見聞きしている先生は多くいます。小・中規模の学校だったら職員室が狭いでしょうし、話す内容がなおさらですね。
職員室での振る舞いスキルはこれです。
担任(や授業者)をたてる
具体的にはこんな感じです。(※相手の先生が年下か年上かで若干言葉遣いは変わります。そこはあなたが使い分けてくださいね)
- 「〇〇先生、Aさんへの声かけありがとう!今日も時間通り指導を始めることができたわ。」
- 「Aさん、指導していても落ち着いて心が安定してるのが分かる。クラスではどう?」
- 「〇〇先生! 今日Aさんが掃除頑張ってたよ!何か指導したの?」 など
これらは、通級に来ている子を通して担任をたてる、の一例です。
担任は、クラスの子が褒められたら自分が褒められているような気がするものです。あなたも学級担任をしていた時、そうだったでしょう?
だから通級に来ている子どもの言動を積極的に褒める。まずはこれが大事です。
次は、直接担任をたてる、の例を紹介します。
- 「先生がそんな風にクラスで支援してくれてるから、Aさんは安心して生活できてると思うよ。」
- 「この前先生が〇〇に困ってるって教えてくれたから、この指導を開始できたよ。ありがとう。」
- 「この前のトラブルについて、通級ではこんな風にAさんに指導しました。これで良かったですか?」 など
担任には一人ひとりポリシーや教育観があります。それを重視した上で話すことが大事です。
もちろん、あなたにも通級担当としてのポリシーや教育観があるのは分かります。伝えたいこと、言いたいこと、「もっとこうしてよ…!!」があることも分かります。
だけど、まずは担任のポリシーや教育観を重視する。つまり、担任をたてる。
これが通級担当としての1つ目の振る舞いスキルであり、最も大切です。
場面②:授業の行動観察
空き時間があれば、行動観察に行くことがありますね。
その時にも、通級担当としての振る舞いスキルがあります。
担任(や授業者)の邪魔をしない
行動観察の目的は何ですか?
それは、「通級に来ている子が学級でどのように学習・生活しているかを確認するため」です。
だから、以下のような行動はNGです。
- 授業内容について、途中で口を挟む
- 授業中の指示や説明に対して、首をかしげる・ブツブツ呟く
- 教室前方や担任の動線上に立つ など
あなたが学級担任だったら、こんなことされたら嫌でしょ?
行動観察に来てほしくないよね(笑)
では、どんな振る舞いスキルが必要なのか?
- 授業中は黙る。また、担任は見ずに通級に来ている子を中心に見る
- 通級に来ている子の反応を観察する(※説明を聞いているか、指示に反応しているか等)
- 基本的には、視界的も動線的にも邪魔にならない教室後方や隅に立つ
- 担任が忙しそうで手が足りなさそうであれば、通級に来ている子のサポートをする(※問題の解説をする、取り組むように声かけする等) など
イメージできますか? 行動観察とはいえ、担任からしたら授業を見られるのはなんか嫌。
その気持ちに配慮して、邪魔をしない。
担任の邪魔をしないように行動する。
これが、通級担当としての2つ目の振る舞いスキルです。
場面③:通級での指導
実際の指導での振る舞いスキルはこれです。
担任の教育観や学級のルールを確認する
具体的にはこんな問いかけになります。
- 「学級ではどんなルールになってるかな?」
- 「この前も同じようなことがあったと思うんだけど、その時〇〇先生はなんて言っておられた?」
- 「〇〇先生は、あなただったら△△という目標がいいんじゃないかって言っておられるんだけど、Aさんはどう思う?」 など
その子が学校で一番多くの時間を過ごすのは、何と言っても学級。
だから、学級のルールや担任の教育観などに基づいてルールを解説したり、目標を設定したりすることでその子が楽しく学校生活を送れる可能性が高まります。
担任の教育観や学級のルールを確認する。
これが、通級担当としての3つ目の振る舞いスキルです。
まとめ:明日から実践できる!「振る舞いスキル」
通級担当は主役ではなく黒子。
その視点を日々の振る舞いに落とし込むことで、担任や子どもとの関係はぐっと安定します。
今回紹介した3つの振る舞いスキルは、
- 職員室で担任をたてること
- 行動観察の場面では担任の邪魔をしないこと
- 担任の教育観や学級のルールを確認して指導・支援に生かすこと
どれも小さな実践ですが、積み重ねると確かな信頼につながります。
「振る舞い」は特別な才能ではなく、意識次第で誰でも実行できるスキルです。
まずは明日から。
まずは一つの場面だけでもいいから取り入れてみてください。
その積み重ねが、あなたの信頼と通級担当としてのやりがいにつながりますよ。
一緒に頑張っていきましょう。
👉 関連記事:
👉 通級ラボのトップページはこちら
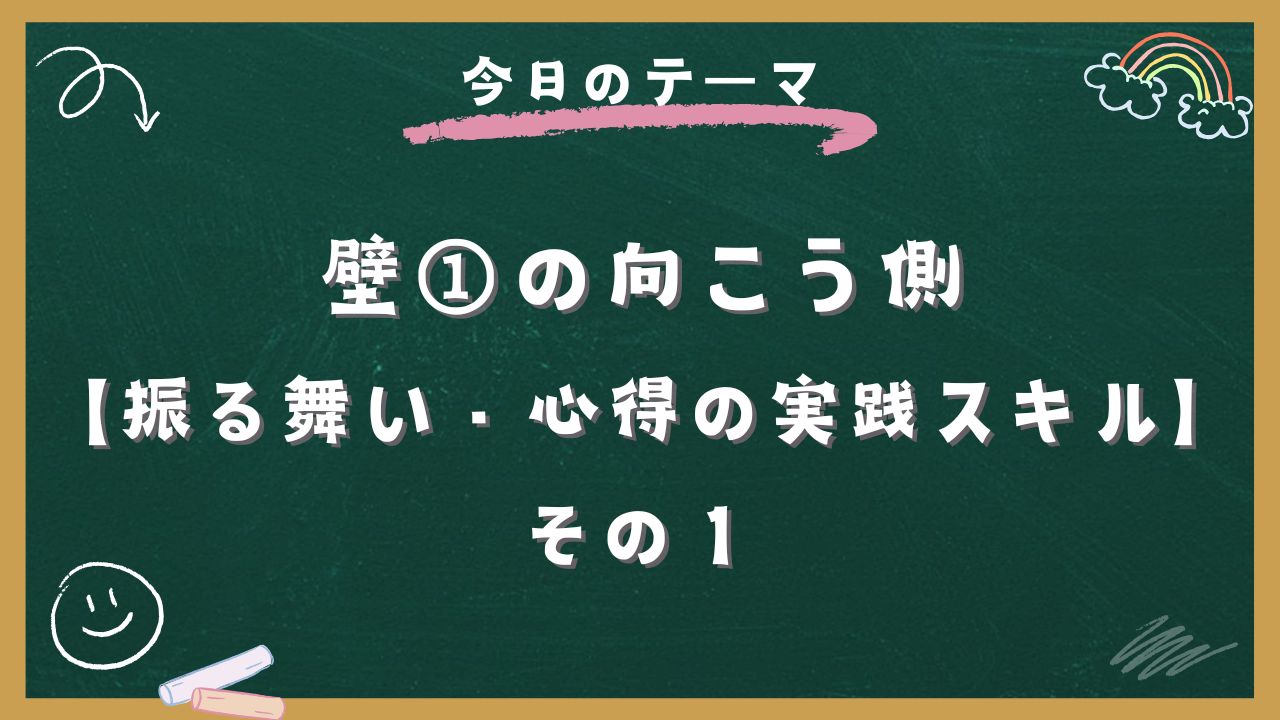


コメント